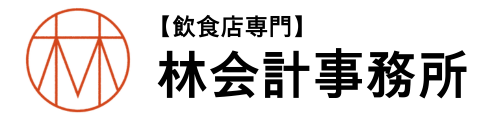飲食店の適正在庫とは?資金繰りが楽になる棚卸の極意

弊所では、毎月末に棚卸をすることをおススメしています。
その理由は、毎月の試算表を作成するという表向きの理由もありますが、実は棚卸を実施するの回数の多いお店は資金繰りに苦労しないという事実を知っているからです。
この記事では、具体的な事例を紹介しています。
取り入れられそうなものから、やってみてください。
きっと、3か月後には、資金繰りが楽になった実感を得られますよ。
まず、正しい棚卸ができているお店は、売上の多寡にかかわらず、資金繰りに苦労していません。
逆に、正しい棚卸ができていないお店は、売上が多くても、資金繰りに悩んでいます。
中には「毎月末に棚卸をしているけど、相変わらず資金繰りが厳しくって、、、。」
とおっしゃる方が居ますが、それは正しい棚卸ができていないからです。
では、正しい棚卸とは?
その前に、「棚卸」を定義します。
「棚卸」とは、売上としてお客さんに消費されることなく、店内にとどまっているモノを全て拾い集めて、数量ではなく金額に換算することです。
ですから、食材に限らず、包材や紙ナプキン、ストローや予備の食器なども含まれます。
つまり、お金を払って手に入れたもので、売上に貢献していないモノは全て「棚卸」です。
経理上、厳密に言えば、食材以外のものは「貯蔵品」になりますが、それを区別するメリットは中小規模飲食店にはありませんので、この記事では「棚卸」という表記に統一します。
次に、正しい「棚卸」ですが
定義に沿って、店内に残っているモノを全て拾うことです。
多分、あなたが今までやってきた「棚卸」より拾う品目は多いでしょう。
って言うか、拾う項目が多いからお金が無いんです。
「棚卸」を楽にするためにも、店内のストックを減らしていきましょう。
それが結果として、お金の流れをスムーズにして資金繰りの改善に貢献してくれます。
適正な棚卸量を知る
まず一度、正しい「棚卸」を体験してみてください。
ただ、算出された「棚卸」の金額が多いのかどうか?
多いって、どれくらい多いの??
と、疑問に思われるでしょう。
そこで計算して欲しいのが
あなたのお店の適正棚卸量です。
健康診断を受診するとその結果には、必ず基準値が示してあり、その数字内であれば問題なしと判定されます。
それと同様に、各店舗の棚卸量も店舗の実態に応じて、適正値があります。
適正な棚卸量かどうかは、棚卸が何日分の売上に相当するのかで判定します。
飲食店では一般的に、3~5日分の売上に相当する棚卸量が理想とされます。
棚卸量の計算方法と必要なデータ
では、具体的にお店の棚卸高が適切な棚卸量かどうかを見ていきましょう。
棚卸量が売上の何日分かを計算するために、必要なデータと計算方法は以下の通りです。
必要なデータ
- 当月末棚卸高:当月末に拾った棚卸の結果を集計した金額です
- 当月の原価率:当月の売上高に占める仕入原価の割合です
- 当月売上高:当月の総売上高です
- 当月の営業日数:実際に営業した日数です
計算式と具体例
では、この計算式に当てはめて、現在の棚卸量がお店の売上に対して何日分あるかを算出してみましょう。
棚卸量 = (当月末棚卸高 ÷ 当月の原価率) ÷ (当月売上高 ÷ 当月の営業日数)
例として以下のデータを使って計算してみます。
- 当月末棚卸高:525千円
- 当月の原価率:35%
- 当月売上高:11,250千円
- 当月の営業日数:30日
(525千円 ÷ 35%) ÷ (11,250千円 ÷ 30日)
=1,500千円 ÷ 375千円
=4日
この場合、棚卸量は4日分となり、一般的な3~5日分以内に収まっているため「適正」と判定されます。
是非、一度計算してみてください。
過剰在庫のリスクとその解消法
計算した棚卸量が6日分を超える場合は、過剰在庫の兆候があるため要注意です。
たまたま、その月末だけ6日分を超えている場合がありますから、軽々に過剰在庫とは言い切れませんが、6日分以上が常態化しているようでしたら、下記に紹介している事例などを参考に、小さなことからでいいので手を打っていきましょう。
過剰在庫がもたらすリスク
購入したモノの代金は、その食材が売り上げに貢献するか否かに関係なく、購入時又は、決まった日付で〆られ、翌月に支払われます。つまり、先払いです。
↓
月末にそのモノが残っていれば、それは、今月の売上原価ではなく棚卸です。
↓
棚卸は、一見、残りモノでしかありませんが
財務的に考えると⇒お金は出て行ったけど、それに見合う売上入金がまだの
未収入金の塊です。
貯『金』なら腐りませんし、僅かながら利子も見込めますが
貯『棚卸』は腐るだけ。
腐った「棚卸」を見つけたら破棄しますよね。
棚卸の破棄は、財務的にはお金をドブに捨てるのと同じ意味です。

つまり、過剰在庫の状態が続くと
- キャッシュフローの悪化:資金が「棚卸」として塩漬けになるため、他の支払いに回す余裕が減ります。
- 廃棄リスクの増加:賞味期限が短くなり、ロスにつながりやすい棚卸が増える。
正しい棚卸の実施で、飲食店経営の黄色信号を見落とさないようにして行きましょう。
実践事例:棚卸量の最適化で改善された資金繰りと労働環境
なまじ置き場所があると、人はその空間を埋めようと、モノを置きたくなります。
今回の事例では、置き場所自体を減らしました。
そもそも、置き場所がなければ買いませんものね。
ある飲食店で、毎月末の棚卸量が6日分以上が常態化していました。
原因を調査すると、未使用の棚卸が多く、管理も行き届いていない状況でした。
この店舗では食材棚を整理し、いくつかの棚を撤去することを提案しました。
棚を減らす案には当初反対意見もありましたが、結果として以下の改善が確認され、労働環境が向上しました。
- 欠品の発生なし:棚を減らしても欠品は発生しなかった
- 店舗内の動線が向上:余分な棚がなくなり作業がスムーズになった
- 資金繰りの改善:不要な棚卸品が減ったことで、経営の負担が軽減された
よくある話:今、要らないものは買わない
『1個買うと1000円だけど、2個買うと1500円』って売り文句を聞いて、1個でいいのに2個の購入を決める。
この時、頭の中では「1個当たり250円も仕入を抑えられた!」っと計算しているでしょう。
気持ちは判りますが、これは過剰在庫の温床です。
もう少し分解して見ていきましょう。
もしこれが、1個消費するのに1ヶ月かかるとします。
2個目の封を開けた時点で購入から既に1ヶ月経っています。
その間、業者で温度管理等完備されていた倉庫で保存されていたならまだしも、あなたのお店の倉庫で保存されていたんですよ。
フツーに考えて、封を開けた時点で、多少なりとも劣化していると判断できますよね。
でもって、その状態から使い切るまでにもう1ヶ月・・・
もしかしたら使い切る前に破棄されるかもしれませんよね。
って考えたら、多少割高であっても必要量をこまめに購入する方が、過剰在庫を生まない、上手な仕入と言えます。
棚卸品の指定席を決める
倉庫や冷蔵庫内に決めた置き場所に、マグネツトや仕切り板などを使って、表札付きの指定席を確保します。
指定席を確保することで、余分にストックすることができなくなります。
又、残量が一目で分かるので、誤発注を防ぎます。
(注)どんなにスペースが空いているからと言って、指定席以外の場所には置かない。
この方法に慣れてくると発注者は、表札の下のある量を確認して注文をするようになります。
仮に、隣の食材が仮置きしてあっても、指定席の食材があるものと思い込んでしまい、注文を先延ばしにする可能性があります。
実際に使う段になって、隣の食材だった!ってことで
欠品が出る可能性があります。
空席には、空席の意味がありますから、勝手に他の物を置かないルールを徹底してください。
調味料の容量を減らす
頻繁に購入しない食材は、劣化防止の観点から、容量を小さいものにできないか調べる。
飲食店だからと言って、必ず業務用を使わなくてはいけない訳ではありません。
たまには、近所のスーパーも覗いてみてください。
継続的な見直しで経営力をアップさせよう
棚卸の実施と棚卸量の見直しは、飲食店経営において重要な役割を果たします。
過不足のない棚卸量を維持することで、売上機会の損失を防ぎ、フレッシュな食材でお客様に満足していただけます。
定期的に棚卸量を見直し、無駄が見つかれば発注頻度を調整するなどして、常に適正な棚卸量を維持しましょう。
ご質問等があれば、気軽にお問い合わせください。